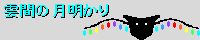東方SS書きである紅雨霽月のブログです。
東方やらラノベやらフリーゲームやら日常のことやらジャンルにはあまり捕らわれてないです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
無駄に長い小説っぽい何か。
一時間半もかけて私は結局何が書きたかったんだろうか。
そんな作者本人も何を狙ったのか分からない上に誤字脱字、話の矛盾を一切チェックしていない落書きを読みたい方は「続きを読む」からどうぞ。
つい最近、うちの学校に幽霊が出るようになったらしい。
信憑性はかなり薄い。というか信憑性の高い幽霊話があるのだろうか。
まあ、そんな信憑性云々はどうだっていい。
私にとって重要なのはどれだけの人間が、どれだけその噂を信じてるのかってこと。
そして、実際にそれを確かめようっていう馬鹿がどれだけいるのかってこと。
ただそれだけ。
耳を澄まして、周りの声を聞く。
ぼんやりしていれば、何も聞き取れなくとも、集中すればそれなりに聞き取れるようになって来る。
目もつむる。今は視神経に余計な労力を割く必要はない。
味覚も嗅覚も触覚も必要ない。ただ、聴覚だけが働いていれば良い。
・・・ふむ、何人かの馬鹿どもが幽霊を探そうって息巻いてるみたいね。
実際に行動に移すかどうかは、三対七、ってところ。
三が実行するで七が実行しないね。
あんまり期待は出来そうにないわね。
でも、用意だけはしておこうか。
久々の獲物なんだから。
◆
入り口付近に電球を吊るして完成。
パニック寸前の状態ならこんな簡単な物でも勘違いしてくれるだろう。
私がしていたのは、肝試しの準備だ。
幽霊の噂話が広まっていることを良いことに私はそれを信じてもしくは疑って行動する連中を驚かして楽しんでいるのだ。
とはいえ、毎日そういう連中が来るわけじゃない。
学校で幽霊探しの計画を立てているのを聞いたとき、もしくは暇で暇で仕方ないときにこういうことをしている。
片付けるの面倒くさいから。
今のところ引っ掛けたのは四グループくらい。
皆が皆、疑いながらも幽霊っていうのを意識しすぎてるせいか面白いくらいに驚いてくれた。
それが癖になったからこそ、確実に人が来るのを見込めなくとも、片付けるのが面倒だろうと私は続けている。
私は二階の教室から校庭を見下ろして誰かが来るのを待つ。
扉の鍵を外して正面からだけ入れるようにしてるのだ。だから、他の場所を見張っている必要はない。
私はじーっと校庭を見つめる。
動くものが何もないから一切の音が死んでしまう。
幽霊を信じてるのはこういう静寂に恐怖を感じるんだろうな、ってぼんやりと思う。
・・・・・・
何も起きないまま、一時間が過ぎる。
どうやら、昼に計画を立ててたあいつらは来るのを止めたようだ。
七割がた来ないだろうと思っていたから落胆はない。ただ――
「面倒ね」
そう、用意した仕掛けの数々を片付けなければいけない。
その面倒くささを想像して、私は思わず声にしてしまった。
誰にも届かない声は空気の中へと溶けていく。そのはずだった。
「何が面倒なの?」
不意に声が聞こえた。
その声は近くから聞こえてきているのか、遠くから聞こえてきてるのか良く分からない声だった。
けど、その声は私の後ろから聞こえてきて、声の持ち主が私と同性である、ということはわかった。
どうやって私に気付かれずにここまで来たかは分からないけど、折角だ。片付けを手伝ってもらおう。
「仕掛けの片付けよ。よかったら、手伝って・・・」
振り返って、私は固まってしまう。
だって、そこにいたのが正真正銘の女の子の幽霊だったから。
いやいや、ありえない。そんなことは絶対にありえない。
身体が半透明で、宙から浮いてるだなんて。
「おーい。どうしたの? 途中で固まって」
何かが私の前までやってきて顔の前で手を振っている。
移動する際、かなりスームズで紐に吊られているような様子は一切なかった。
「んー? もしかして、夢だとでも思ってんの? そーんなことないよ。ここは正真正銘の現実だよ」
幽霊が笑顔を浮かべた。
「・・・あなた、幽霊?」
恐る恐る口を開いてみる。
「うん、そだよ」
そっかぁ、とここで納得できるほど私の頭は単純には出来ていない。
それとも、この状況でも幽霊を信じられないっていうのは頭が固いってことなんだろうか。
どっちなのか、という判断が付けられるはずもない。
とりあえず、私が言えるのは、
「じゃあ、片付け、手伝ってくれるかしら?」
そんなことだった。
前後が繋がってない上に、じゃあ、の意味がわからなかった。
「いいよ」
それでも幽霊は笑顔で頷いてくれたのだった。
◆
「ありがとう、助かったわ」
最初にいた教室で私は幽霊へとお礼を言う。
一緒に作業をしていて思ったんだけど、かなり話しやすい子だった。
「いえいえ、どういたしまして。私も久々に誰かと話せて楽しかったよ」
あの子が本当に楽しげに笑顔を浮かべる。
皆、幽霊は悪いやつだ、って決め付けてるみたいだけど、その認識を改める必要がありそうだ。
「じゃあ、私は帰るわね。また、明日にでも遊びに来るわ」
そう言って荷物を担いで部屋から出ようとした。
「・・・あれ?」
けど、教室の扉が開かなかった。どれだけ力を入れようとも扉はびくともしない。
え? ちょっと、待って。
おかしいおかしいおかしい。絶対におかしい!
私が手をかけた扉は外から鍵を使わない限り鍵が掛からない扉だ。
そもそも、私は鍵を掛けた記憶さえもない。
「・・・ふふ、逃がさないよ。折角の獲物なんだから」
振り返ってみると、幽霊が楽しげな笑顔を浮かべていた。
けど、滲み出る雰囲気は今まで見てきたのと全く異なってきている。
「どうしたの? 怖いの? 怖いんだぁ」
笑顔のまま近づいてくる。
無意識に一歩後ずさる。けど、後ろには扉。
「・・・私を、どうするつもり」
「どうしようかなぁ。最後には殺しちゃうつもりだけど、出来るだけ恐怖に歪んだ顔を見たいなぁ」
玩具を前にした子供のような笑顔。
けど、向ける対象は私。そして望んでいるのは私の恐怖。
何をするつもりなのか、幽霊に何が出来るのかなんてわからない。
けど、早くここから逃げないと、と全ての全身が全霊で警笛を鳴らしてる。
「・・・」
動こうとする。けど、身体が動かない。
声を出そうとする。けど、口から一切の音が出ない。
「ふふ、いいねぇ、いいねぇ。その顔。もっと、もっと歪ませてよ」
いや、いや。
近づいてこないで。
もう何もしないで。
誰かをからかって楽しむんじゃなかった。
話しやすいからといって幽霊を信用するんじゃなかった。
幽霊の両手が私の首に触れる。
冷たいけど確かにその感触を感じる。
「暖かいね。あなたは。でも、私がきゅっと絞めちゃったら冷たくなっちゃうんだよね」
嬲り殺すかのようにゆっくりと両手に力が込められる。
苦しい、苦しい。
殺すなら早く、殺してよ。
苦しいばかりで、終わりが近づいてきているようには感じられない。
やだ。苦しいのなんてやだ。
早く。殺すなら早くして!
苦悶も叫びも願いも声にはならず、苦しさに悶えることも出来ない。
気が付けば何も見えなくなってる。今の私には苦しさしかない。
ねえ、終わるのはいつ。
早く終わらせて。
このままだと狂ってしまう。
苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい・・・。
今の私にはそれしかない。
「おやすみなさい」
それは、救いの言葉だった。
PR
この記事にコメントする